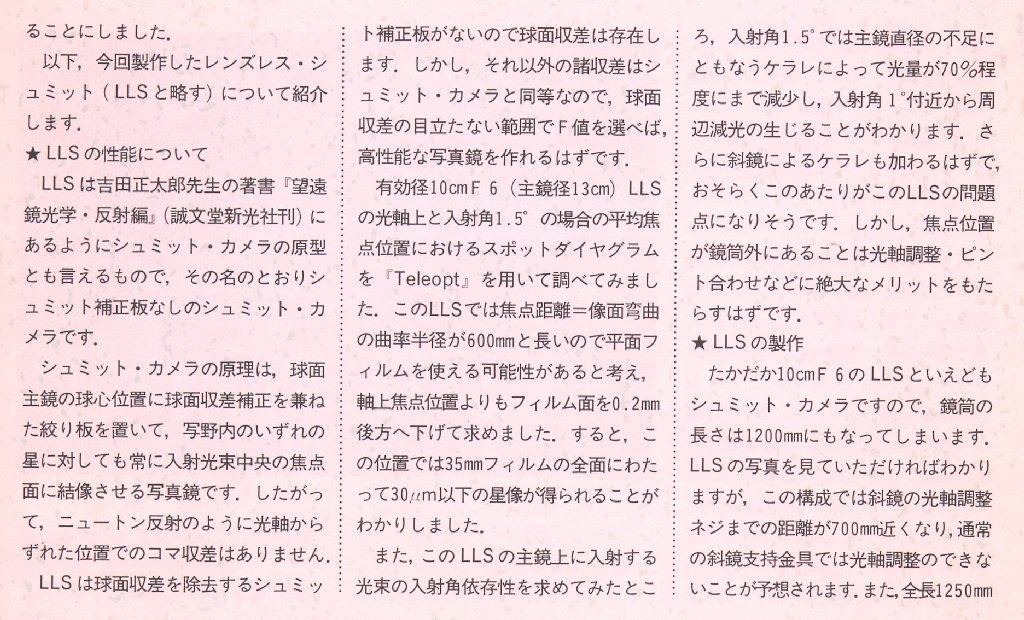1991年の夏、fl=500mmクラスの星野カメラとして製作した10cm・F5ニュートンのコマ収差にガッカリして製作を思い立ったのがちょっと珍しいレンズレス・シュミットカメラ
(LLS) でした。LLSは補正レンズがないことを除けば当時高性能な星野カメラの代名詞であったJSOの16cmシュミットカメラと同じ原理ということになり、コマ収差のない良像が得られるものと考えました。
利用するミラーは自作の13cm・fl=600mm球面鏡、これを10cmに絞ってF6の鏡筒を製作しました。
LLSの製作に当たっては当時天文ガイドで領布していた光学設計ソフトの『TeleOpt』を使っていろいろ実験したところ、10cm・F6ならば平面フィルムでもフィルム粒子レベルの星像の得られることが判りましたので、ニュートン反射に近い、できる限り簡易なシュミットカメラを目指すことにしました。
そして、この鏡筒の製作経験と設計実績はFriendship-160ニュートン反射望遠鏡の製作に大いに役立ちました。
以下、1992年3月号の『天文ガイド』に掲載された記事と、このLLSで撮影した星野写真の事例をご紹介します。

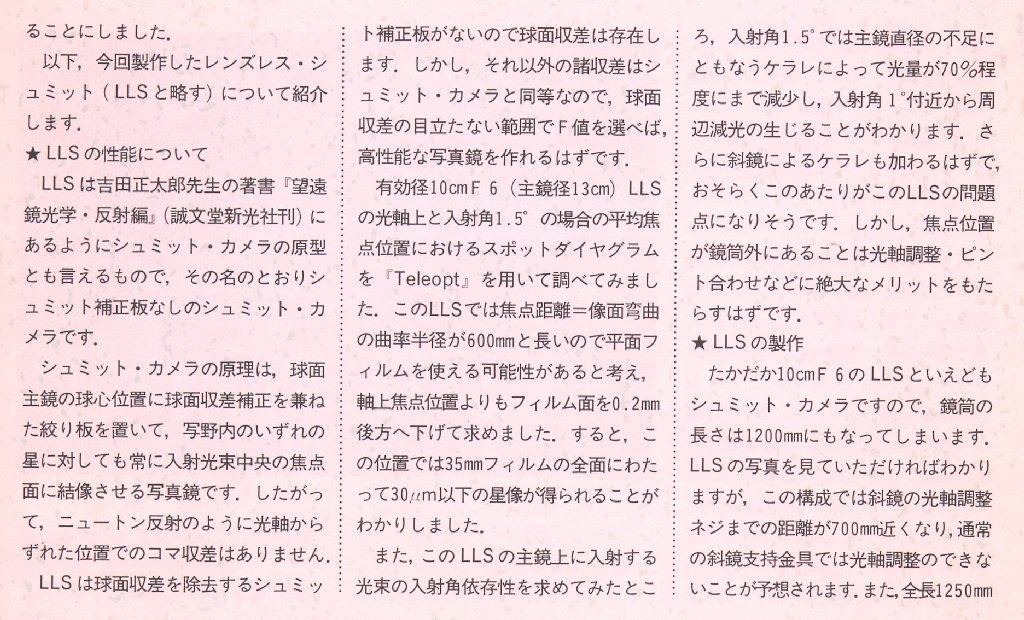

次の作例は記事の中にも掲載されているこぎつね座のM27アレイ状星雲です。フィルムは水素増感したコニカDD-400ですが、周辺減光は目立つものの、中心から周辺まで微光星のサイズはフィルム粒子に近いレベルであることが判ります。もちろん、最周辺部までコマ収差の発生は認められませんでした。

次の作例はオリオン座のM42付近を撮影したものですが、こちらもそれなりに『シュミットカメラ』の星像になっています。ただ、フィルムの中間領域で焦点を合わせるのは意外と大変で、JSOの16cmシュミットカメラを使っておられる多くの方がピント出しにご苦労されていたことを私も味わうことができました。

機材の自作コーナーに戻る