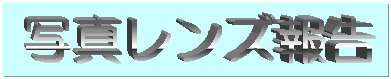
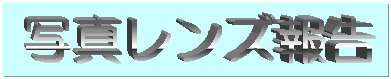
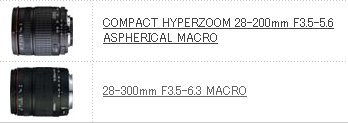 シグマのカタログのズーム2本
シグマのカタログのズーム2本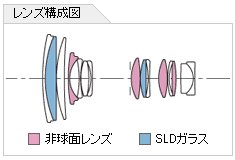 シグマのカタログに掲載されたレンズ構成図
シグマのカタログに掲載されたレンズ構成図 EF-S 18-55mm(18mm)で撮影した水星と金星(開放、3秒)
EF-S 18-55mm(18mm)で撮影した水星と金星(開放、3秒)



 記載のズームリング位置にて撮影(開放、60秒)
記載のズームリング位置にて撮影(開放、60秒)
 彗星拡大(開放、60秒)
彗星拡大(開放、60秒)
 彗星拡大(開放、60秒)
彗星拡大(開放、60秒) FCT-65+Reducer (fl=240mm、30秒)
FCT-65+Reducer (fl=240mm、30秒) Sigma28-300(300) のM42、流れてしまいましたが(開放、180秒)
Sigma28-300(300) のM42、流れてしまいましたが(開放、180秒) FCT-65+Reducer のM42 (fl=240mm、180秒)
FCT-65+Reducer のM42 (fl=240mm、180秒) FCT-65+Reducer のマックホルツ彗星 (fl=240mm、180秒)
FCT-65+Reducer のマックホルツ彗星 (fl=240mm、180秒) Sigma 28-300 (100mm)
F5.6
ISO400相当 露出180秒
Sigma 28-300 (100mm)
F5.6
ISO400相当 露出180秒