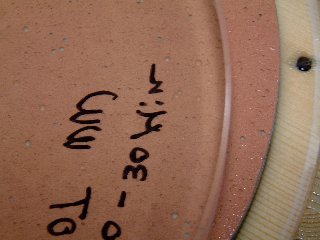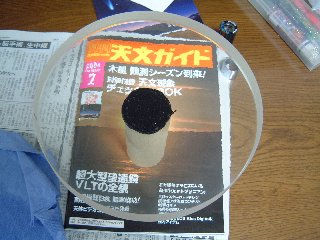5.磨き(パッド研磨による砂目つぶし)
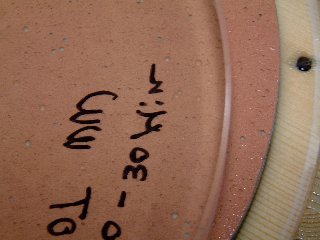
 磨きは最初の方でご紹介いたしました半導体などの上は研磨を行うときに用いられる『研磨パッド』を使ってみることにします。初めての経
験なので「ダメなら#1000に戻ればいいや」という『軽いノリ』で試してみることにしました。
磨きは最初の方でご紹介いたしました半導体などの上は研磨を行うときに用いられる『研磨パッド』を使ってみることにします。初めての経
験なので「ダメなら#1000に戻ればいいや」という『軽いノリ』で試してみることにしました。
さすがにこのパッド、平面精度の要求される半導体用なので厚みの均一性も良いようで、盤材に貼り付けてカッターナイフで円周を切りそろえただけで鏡材が
吸い付くような面の整合性です。水だけ与えて10分ほどドレッシング(馴染ませるための空ずり)をしましたが、当りの状態は変化しないので恐る恐るセポー
ルを入れて30分ほど研磨したものが次の写真です。
 まだ全体が磨けていません。中央部の当たりが僅かに多いようです。球面に対して多少浅いのかもしれません。あるいは1/3ストロークで
磨いたためかもしれません。
まだ全体が磨けていません。中央部の当たりが僅かに多いようです。球面に対して多少浅いのかもしれません。あるいは1/3ストロークで
磨いたためかもしれません。
でも中央から確実に研磨が進んでいることと、研磨パッドで気なっていた『端ダレ』は今のところないようなのでこのまましばらく進んで、とりあえずフー
コーテストにかけられる状態のところまで持っていってみようと思います。
2004/01/11
研磨パッド+セポールの組み合わせでそれなりに『磨き=ポリッシング』が上手くいきそうなので通算180分の磨き作業を進めました。
研磨剤
|
研磨時間(積算) 分
|
通算研磨時間 分
|
研磨方法
|
研磨運動
|
砂目の状態
|
セポール
|
60 (90)
|
980
|
MOT
|
F
|
|
セポール
|
60 (150)
|
1040
|
MOT
|
D+F
|
|
セポール
|
30 (180)
|
1070
|
MOT
|
D+F
|
|

 今日から木製ハンドルを付けて本格的な研磨作業をします。上の写真の右側はポリッシング90分目の鏡の状態です。まだ鏡面全体が白く
濁っていて、十分に砂目が取れていません。
今日から木製ハンドルを付けて本格的な研磨作業をします。上の写真の右側はポリッシング90分目の鏡の状態です。まだ鏡面全体が白く
濁っていて、十分に砂目が取れていません。

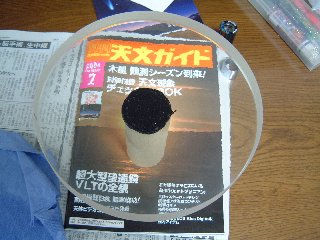
上の左の写真は150分目の鏡面です。この状態でも周辺部にかなりの砂目が残っています。しかし、中央部にはどのような角度から見ても砂目の存在は見ら
れなくなりましたので、今後の砂目評価は中央部をベンチマークにします。
右の写真はポリッシング180分目の鏡面です。150分の時の鏡面と比べると周辺の砂目の大きさは半分位まで小さくなっています。また、中間帯の砂目も
ほとんど見当たらなくなりました。早く鏡面の形状をフーコーテストしてみたいのですが、面の良し悪しの度合いを知ってしまうと『止め時』に手心が加わって
しまって砂目を十分に取りきれないような事態が起こるかもしれません。
ここはテストしたい気持ちをグッと押さえて完全に砂目がなくなるまでポリッシングを継続することにします。
2004/01/12-13
何としても砂目が完全になくなるまで・・・と頑張ってきた研磨もいよいよ最終段階です。1/12は180分間のポリッシングをしました。回転運動とWW
運動の組み合わせです。回転運動では周辺部に多少力を加えながら砂目を潰すようにMOTで研磨をしながら様子を見て、周辺の砂目が徐々に減ってきたところ
で滑らせるだけのWW運動のTOTを都合90分間、これでほぼ完全に砂目がなくなりました。
研磨剤
|
研磨時間(積算) 分
|
通算研磨時間 分
|
研磨方法
|
研磨運動
|
砂目の状態
|
セポール
|
60 (240)
|
1030
|
MOT
|
D+F
|
|
セポール
|
30 (270)
|
1030
|
MOT
|
D+F
|
|
セポール
|
30 (300)
|
1090
|
TOT
|
D+F
|
|
セポール
|
30 (330)
|
1120
|
MOT
|
B+F
|
|
セポール
|
30 (360)
|
1150
|
TOT
|
B+F
|
|
セポール
|
30 (390)
|
1180
|
TOT
|
B+F
|
○
|
 研磨剤の混入など十分に注意していましたので鏡面にスクラッチやスリークは入っていません。また、研磨パッドで一番気になっていた周辺
のダレも『見た目』ではほとんど無いようです。
研磨剤の混入など十分に注意していましたので鏡面にスクラッチやスリークは入っていません。また、研磨パッドで一番気になっていた周辺
のダレも『見た目』ではほとんど無いようです。

そこで、簡易的に製作したフーコーテスタで鏡面状態の確認を行うことにしました。簡易的とはいってもこのフーコーテスタは前後に15cm移動可能な精密
微動テーブルの上にもう一つ10μm単位で読み取り可能な微動ユニットを載せた本格的なものです。光源には高輝度緑色LEDを使っています。
先ずこれで球心位置を測定したところ、半径は3900mmでした。結局、焦点距離は1950mm、F9.75ということになって公約のF10に近い鏡で
した。そして、球心位置で恐る恐るナイフエッジを切るとほぼ全面、一瞬にして真っ暗になり予定通り球面になっていることも確認できました。