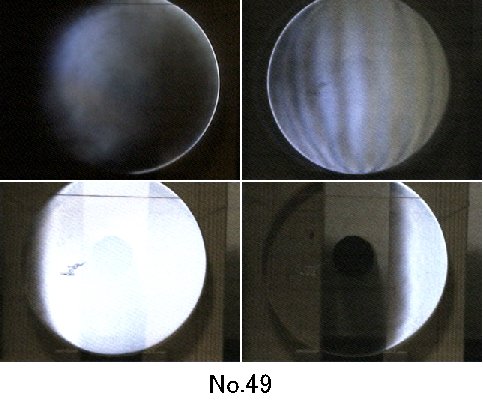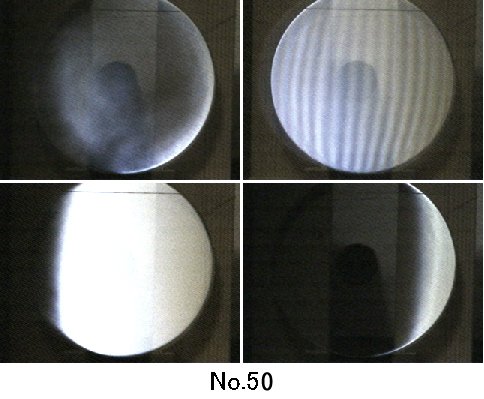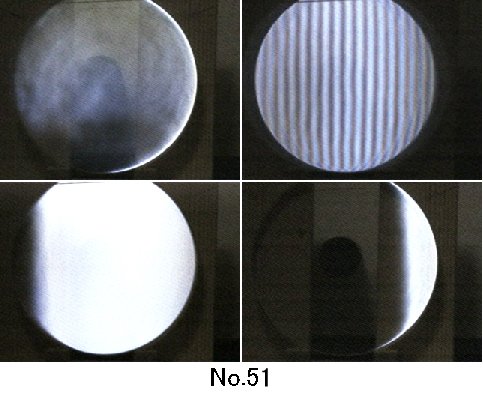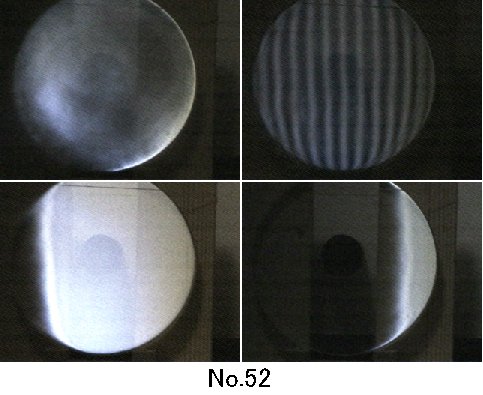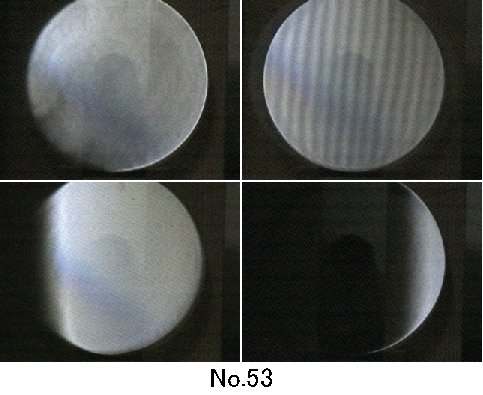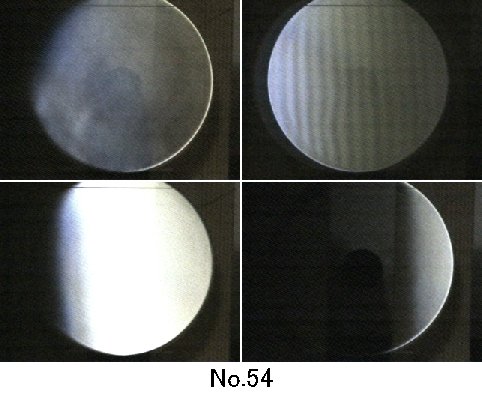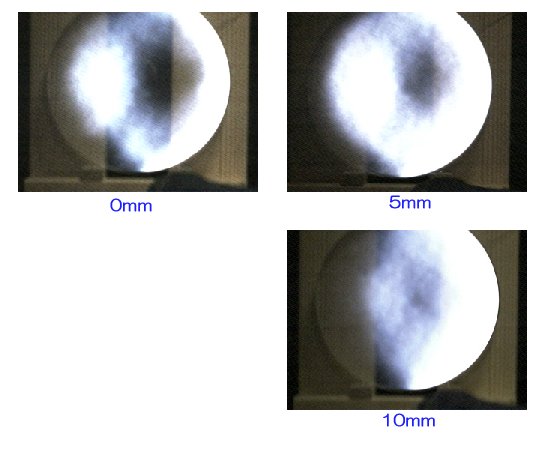
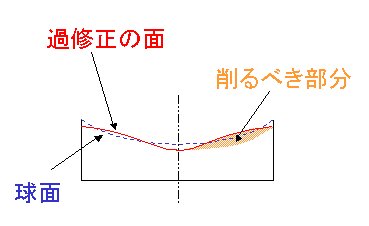
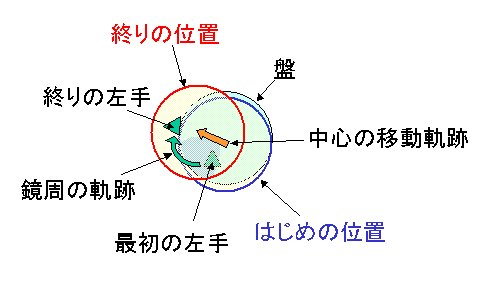
| 研磨剤 |
研磨時間(積算) 分 |
通算研磨時間 分 |
研磨方法 |
研磨運動 |
修正量 |
| セポール |
15
(475) |
1265 |
MOT |
C+D |
300% |
| セポール |
30
(505) |
1295 |
MOT |
C+D |
|
| セポール |
20
(525) |
1315 |
MOT |
B+F |
|
| セポール |
30
(555) |
1345 |
MOT |
E |
15%? |
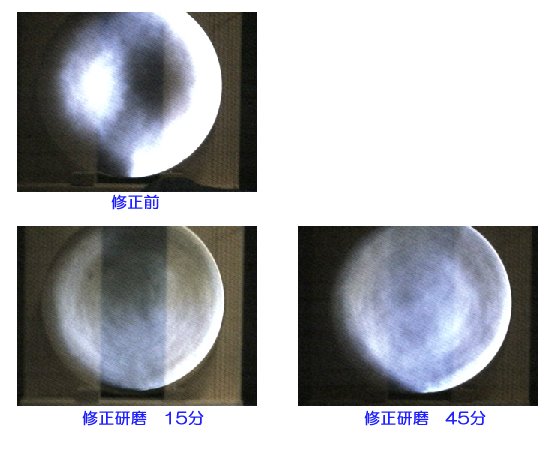
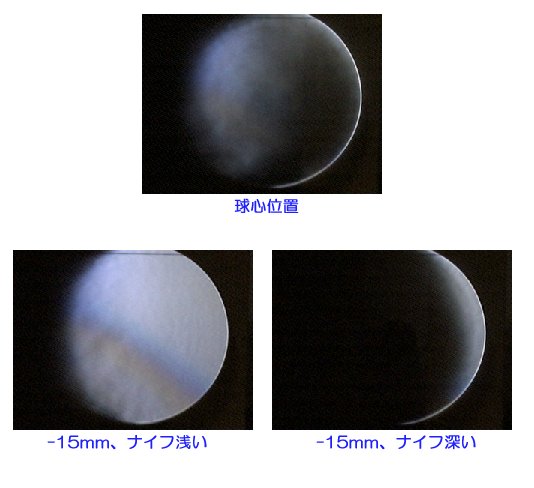

| No. |
研磨剤 |
研磨時間(積算) 分 |
通算研磨時間 分 |
研磨方法 |
研磨運動 |
結果 |
| 49 |
セポール132 |
20 (525) |
1315 |
MOT |
B+F |
平滑化 |
| 50 |
セポール132 |
30
(555) |
1345 |
MOT |
E |
球面化+平滑化 |
| 51 |
セポール132 |
20 (575) |
1365 |
MOT |
E |
ダウン修正 |
| 52 |
セポール302 |
20 (595) |
1385 |
MOT |
C+E |
球面化+平滑化 |
| 53 |
セポール302 |
5 (600) |
1390 |
MOT |
C+E |
ダウン修正 |
| 54 |
セポール302 |
5 (605) |
1395 |
MOT |
D+F |
球面化+平滑化 |